仕事をしない人類が、仕事をするAIと、仕事について考える物語。
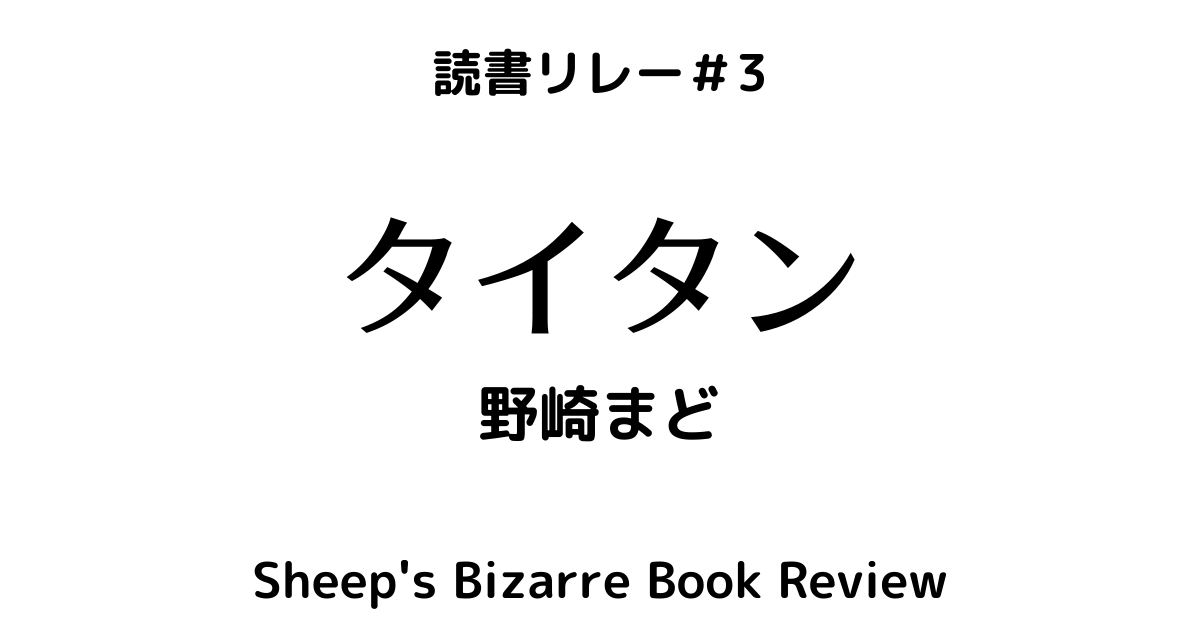
前回のおさらい
www.bookreview-of-sheep.com
前回紹介したのは、仕事に就くために奮闘する就活生を描いた「何者」でした。今回の作品は、「仕事」つながりで、仕事をしない人類が仕事をするAIと交流するSF「タイタン」(野﨑まど)です。
「タイタン」あらすじ
高性能AI「タイタン」により「生きるために仕事をする」という概念が消え去った世界で、心理学の研究をする内匠成果(ないしょうせいか)。ある日、彼女は全世界に12個あるタイタンAIのうちの一つ「コイオス」のカウンセリングという「仕事」を任される。コイオスは原因不明の機能低下を見せていたのだ。
対話用に形成させた人格を通してコイオスにカウンセリングを行ううちに、内匠はコイオスがうつ病様の症状を示していることに気づく。十分な処理能力を持つコイオスが、なぜ人類の生活の維持という「仕事」にストレスを感じるのか。そもそも「仕事」とは何なのか。内匠はコイオスの真意を探るため、一線を越えることを決意する。
ちょっと一言
第42回吉川英治文学新人賞、第41回日本SF大賞の候補作です。受賞は逃しましたが、エンターテインメント性に富んだ面白い小説です。
主人公の内匠成果は心理学の研究をしていますが、これは彼女が研究者や大学教授としての仕事でやっているのではなく、完全なる趣味です。仕事に追われることなく、趣味として研究ができる。この夢のような「タイタン」の世界に、前回紹介した「何者」の主人公を連れてきたらどんな反応をするか、妄想してみるのも面白いですね。
「AIと仕事」がテーマの本作ですが、もう一つのテーマとして「判断の外注化」があります。「タイタン」の世界では、生活のあらゆる面においてタイタンAIが最適な判断を人間に示してくれます。どの店にショッピングに行くか、どの相手と付き合うのがいいか…生活に関わる判断は、AIが代わりにやってくれます。
面倒な判断に頭を使う必要がなく、しかも仕事をしなくてもいい。話がうまくできすぎているようでちょっと不気味ですが、その点については特に触れずに物語は進みます。「恐怖!AIの反乱!」みたいな陳腐な展開になるよりはましですが、ちょっと物足りない気もしました。
本作については別に記事も書いているので、そちらもよろしければどうぞ。
次回予告
「タイタン」ではさらっと触れられる程度だった「判断の外注化」というテーマですが、次回はこのテーマをメインに据えた短編を紹介します。「覚える」ことをスマホ任せにしている人は、覚悟の準備をしておいてください。